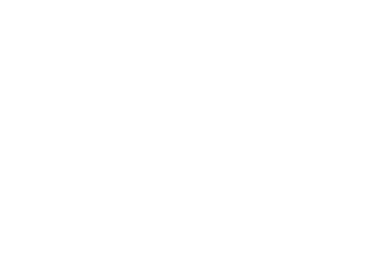タイトル「グリムメイカー」の意味は?

グリムメイカー / 浦島坂田船
グリム童話といえば魔女
「グリムメイカー」というタイトル。
由来が気になります。
”メイカー(maker)”は物を作り出す人。
”グリム”はグリム童話からヒントを得たのでしょう。
グリム童話には「白雪姫」や「ヘンゼルとグレーテル」、「シンデレラ」……。
と枚挙に暇がありません。
ディズニー映画の大半はグリム童話から着想を得ています。
その中の「ヘンゼルとグレーテル」ではお菓子の家と魔女が登場します。
ハロウィンの仮装でも魔女に変身する人がいます。
しかし、グリム童話で魔女は”悪”の象徴。
西洋におけるドラゴンと似た存在として描かれます。
もちろんヘンゼルも魔女によって牢に閉じ込められます。
しかし、魔女は目が悪く、物がよく見えません。
それが幸いして妹のグレーテルは兄のヘンゼルを救出するのです。
浦島坂田船は不可思議なグリムの世界を描きたかったのでしょう。
テーマはハロウィン
死者の祭り
キョンシーや主教(東方正教会)に仮装する浦島坂田船。
ハロウィンは死者の復活がテーマです。
日本でいうところのお盆に相当します。
仮装が目的ではありません。
アメリカは土葬の習慣があるので、棺から死人が蘇ります。
そう考えられているのです。
「お菓子をくれないとイタズラしちゃうぞ」と。
だから子供たちはゾンビやドラキュラに変装するのです。
キョンシーは中国のお化け。
ファンタジーものは好まない中国の文化ですがキョンシーは別です。
主に清朝(17世紀~20世紀初頭)の官服を着ています。
中国は基本的に火葬ですが、位の高い役人や皇帝は土葬です。
そうした人々は不遇の死を遂げることがあり、化けて出ます。
それを具現化したのがキョンシーなのです。
どうして”ハロウィン= かぼちゃ”なの?
MVの後方でぴょんぴょん跳ねるカボチャ。
MV「グリムメイカー」の影の主役です。
どうしてハロウィンになるとカボチャの提灯が登場するのでしょうか?
ハロウィンはアメリカで広く行われています。
しかし、アメリカ合衆国は移民の国。
アイルランド島で飢饉に見舞われたケルト系の民族も移住しました。
当時の食料不足は深刻でした。
その証拠に現在のアイルランド共和国は最盛期の人口を回復していません。
そのアイルランドのハロウィンで使われていたのは”かぶ”。
かぼちゃではなかったのです。
しかし、アメリカに移ったアイルランド人はかぼちゃを転用。
それはかぼちゃの方が取れやすかったからです。
元々アイルランドは痩せた土地。
アイルランド西部ではじゃがいもぐらいしか育ちません。
こうしてアメリカのハロウィンはかぼちゃになったのです。
踊りやすいリズム
作詞作曲はJunky
「グリムメイカー」の曲と歌詞はJunkyが担当。
テンポのよいリズムで踊り出したくなるような曲です。
裏拍での音の入れ方や装飾音のタイミングが絶妙ですね。
また、拍手の音もハロウィン感を演出する効果があります。
まるで舞踏会に招待された貴族のような気分にさせてくれます。
ハロウィンと仮装舞踏会をミックスしたようなメロディー。
普段、音楽になじみのない人でも足でリズムを刻んでしまうことでしょう。
MVのキャラクターが奇想天外
ハロウィンとコスチューム
冥王ハーデース、負傷兵、キョンシー、主教。
どれも死にまつわるキャラクターです。
浦島坂田船のMVをヒントにコスチュームを決めた読者もいるでしょう。
毎年あるイベントなので今年は違うものをと考えます。
そんなときの助け舟ともなるMV「グリムメイカー」。
一貫して”死”をテーマにしたキャラクターが描かれているのは賛嘆します。
彼らなりにハロウィンの意味を理解したのでしょう。
ハッピーハロウィン!