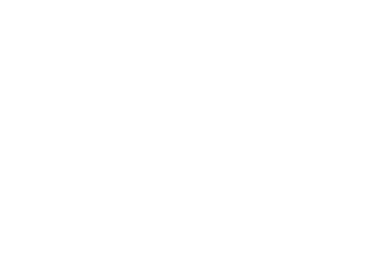ギターを弾いてた ぼんやりといつも
ギターを弾いてた
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
「悪いな」と思ったのは最初だけ。
だからこそ、彼女にわがままを押し付けたあとも「ぼんやり」とギターを弾いていられたのです。
彼女の気持ちにはこれっぽっちも目をくれず、将来のことでも考えていたのでしょう。
彼女は常に自分のそばにいて、消えない存在だと思っていたのかもしれません。
なぜなら、いつも笑っていてくれたから。
思い出から消えた君
ごめんねって言葉
君は聞き飽きてるんじゃないかなぁ?
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
彼女が自分から離れていってしまうとき、彼は何度も「ごめんね」と言ったのかもしれません。
あるいは、これまでにも別の場面で何度も「ごめんね」と言ったことがあるのでしょう。
そのため、聞き飽きて受け入れてくれないかもしれないと考えています。
もう一つ考えられるのが、無意識に気持ちを込めず「ごめんね」を多用していた可能性です。
聞き飽きるほど言ったか、それほどでもないか、彼自身が把握できないぐらい何となく口にしていたのでしょう。
いずれにせよ、謝罪が必要な場面では謝罪をしていたようですね。
どんな風に言えば
優しい君は戻ってくるかなぁ?
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
優しい彼女を自分の元に取り戻したいと考えている彼。
そのためのセリフを考えます。
ここで注目したいのが「優しい君」という言葉です。
優しくて何でも許してくれる相手や、本気で怒っているわけではない相手なら、口先だけの謝罪を受け入れてくれるかもしれません。
しかし今彼女は、彼の元に戻っていません。
つまり彼が犯した罪、彼女に対するぞんざいな態度や仕打ちは、彼女の優しさを持ってしても簡単に許されるものではないのです。
よく出かけた公園を
バスは今通過中
いつかの君が横切る
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
彼を乗せたバスは夜の道を走り、彼女が住む街に近づきました。
二人で散歩に来たことがある公園なのでしょうか。
彼の脳裏に過ったのは、仲良く手を繋いで歩く二人の姿ではありません。
赤信号で停止したバスの前を横切ったのは、彼女の姿。
彼女は一人でバスの前を通過して行きます。
彼の記憶の中で、彼女との別れは相当大きな衝撃だということを表現しているのではないでしょうか。
こうした場面では、思い出の中で手を繋ぐ二人が通り過ぎるのがセオリーかと思います。
しかし彼の思い出の中で、彼女は一人。
隣に並びたいけれど、隣りにいるべき存在ではないと感じているのかもしれません。
二人で過ごす孤独な時間
お互いが別の方を向くようになり、恋人という関係性が揺らぎ始めます。
それを修正するために必要だったのが、二人で過ごす孤独な時間です。
普通の恋人でいたかった
記念日を携帯が知らせてくれて
そんなときばかりうまく立ち回って
誇張して言えば そんな感じだろう
君にしてみれば
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
二人が恋人の関係になった記念日や、彼女の誕生日。
忘れると二人の関係を悪くしかねないこれらの記念日だけは、前もって携帯のリマインダーに登録しておきます。
前日、もしくは当日にはまるでテンプレートのようなお祝いをするのでしょう。
周りから見れば、良い彼氏。彼女だって嬉しくないわけではありません。
この「記念日のエピソード」は、彼女の考えに対して「理解しているよ」とアピールするための例え話でした。
彼は、ここぞという場面で彼女を喜ばせることを忘れなかったようです。
しかし、恋人同士なら当たり前のことではないでしょうか。
彼女は特別な日に優しくしてもらいたかったわけではないのです。
日頃から二人でゆっくりと話しをしたり、彼のギターに合わせてメロディを口ずさんだり、公園に行ったりする。
そんな「普通の恋人同士」でありたかったのではないでしょうか。
「そんな感じだろう」「君にしてみれば」
この言葉から、彼に反省の色が見えないように思うのは私だけでしょうか……。
関係を確認するための非日常
抱き合いながら
僕らは孤独とキスをして
分かったような台詞
ささやきながら眠りに落ちて
朝が来て日常が 僕らを叩き起こし
逃げるようにベッドから這い出る
出典: Another Story/作詞:桜井和寿 作曲:桜井和寿
彼女は微笑んでいても、自分勝手な彼を許しているわけではありません。
彼と見つめ合おうとはしませんでした。
彼は、彼女よりもっと大切な何かを見つめていました。
一つのシーツにくるまっていても、お互いが別の方を向いていたのでしょう。
彼女の言葉には聴いているフリを見せるだけ。何となく適当な返事を返すだけ。
愛の言葉だって、誰もいない空間にそれぞれ身勝手にささやいていました。
それはまるで三文芝居。しかしそれは、二人が恋人同士であることを確認するのに必要な「非日常」でした。
そして朝が来るとともに、非日常が日常に変わります。
虚構のような時間から、いち早く逃げ出します。