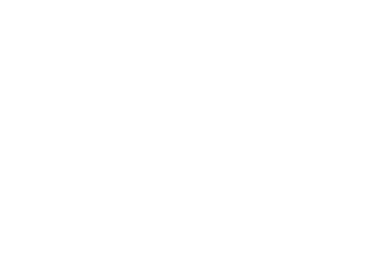加藤登紀子のカバー曲
最初はシングルのB面だった
加藤登紀子のヒット曲「琵琶湖周航の歌」は、1971年5月に発売されたシングル「少年は街を出る」のB面でした。
しかし、曲が作られたのはそれから半世紀も前の1917年(大正6年)年。
この曲は戦後になって多くの歌手がカバーしています。
いわば加藤登紀子の「琵琶湖周航の歌」はリバイバルヒットです。
曲のタイトルにあるとおり琵琶湖を巡った場所を歌に詠んだ歌詞がポイントといえます。
息の長い曲ということだけでなく、曲がたどった道のりには複雑な物語がありました。
旧制高等学校の学生が書いた歌詞
原曲は「ひつじぐさ」

「琵琶湖周航の歌」には1915年に発表された「ひつじぐさ」という原曲があります。
作曲者の吉田千秋がイギリスの詩を日本語に訳した歌詞を付けています。
吉田千秋はプロの作曲家ではなかったのですが、曲を作っては雑誌に投稿していました。
当時はまだレコードが一般に普及しておらず、楽譜と歌詞が雑誌に掲載されて広まったのです。
それを元に読者は歌ったり楽器を演奏していました。
「琵琶湖周航の歌」を作詞した小口太郎は1917年当時、京都にあった第三高等学校の学生でした。
小口の所属するボート部の恒例行事だった琵琶湖巡りの途上で書いたのがこの歌詞。
その歌詞に「ひつじぐさ」のメロディを付けて第三高等学校で愛唱されていました。
曲が広まる切っかけは1933年(昭和8年)に「第三高等学校寮歌」としてレコード化されたこと。
今からさかのぼれば曲が作られたのは100年前。
そのため曲について詳しい経緯は不明な点が多く、研究対象にもなっています。
興味のある方は詳しく解説したサイトがいくつかあるので探してみてください。
歌詞で読み解く琵琶湖の景勝地と小口太郎の想い
出発は志賀(滋賀)の都
われは湖(うみ)の子 さすらいの
旅にしあれば しみじみと
昇る狭霧(さぎり)や さざなみの
志賀の都よ いざさらば
出典: 琵琶湖周航の歌/作詞:小口太郎 作曲:吉田千秋
全体は1番から6番まであり、小口が立ち寄った琵琶湖の景勝地が登場します。
その場所は琵琶湖の南端から西岸を北上し、時計回りで一周するルートです。
歌詞は琵琶湖の南端にある大津の三保ヶ崎がスタート地点。
京都に近く、第三高等学校の小口たちボート部員がスタートを切るには最適でしょう。
1番の冒頭にある歌詞は文部省唱歌「我は海の子」から借用したものだと分かります。
「我は海の子 白波の~♪」で始まる歌ですね。
1910年(明治43年)に小学校の教科書に載ったのが最初で、小口にもお馴染みの曲だったはず。
「琵琶湖周航の歌」は舞台が琵琶湖なので「海」を「湖」に変えて「うみ」と読ませます。
「志賀の都」とは大津のこと。
古くから「滋賀」とは別に「志賀」とも書き表していました。
2006年に大津市に合併されるまで自治体として志賀町があり、湖西線の駅などに名前を留めています。
古代に琵琶湖南西一帯は楽浪(さざなみ)と呼んでいたそうです。
そこから「さざなみの志賀」のように、地名の枕詞(まくらことば)として使われてきました。
平清盛の弟で歌人としても有名な平忠度(ただのり)の和歌。
さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな
-千載集六十六
出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/平忠度
小口が「琵琶湖周航の歌」を書いた大正時代よりもはるか昔からこの言葉はありました。
昔の学生はこういった言葉を使いこなせるほどに古文の素養が身に付いていたのです。
1番を要約すると、大津に別れを告げて、立ち昇る霧とさざ波の湖面にボートを漕ぎ出す情景になります。
ボードで北上する
乙女子は実在するか作者のイメージか
松は緑に 砂白き
雄松(おまつ)が里の 乙女子は
赤い椿の 森陰に
はかない恋に 泣くとかや
出典: 琵琶湖周航の歌/作詞:小口太郎 作曲:吉田千秋
2番の宿泊地は西岸にあり琵琶湖八景の1つに数えられる景勝地の近江舞子。
ここも現在は大津市の一部になっています。
この一帯は雄松と呼ばれ、雄松崎周辺は海水浴場のある砂浜や椿の林が有名です。
ここは、赤い花を咲かせた椿の木陰で少女(乙女子、おとめご)が失恋して泣いていたという言い伝え。
小口が現地でそうした話を聞いたのか。
それとも、雄松の風景に感銘を受けて自分の体験か、心に浮かんだイメージを重ねたものか。
判然としません。