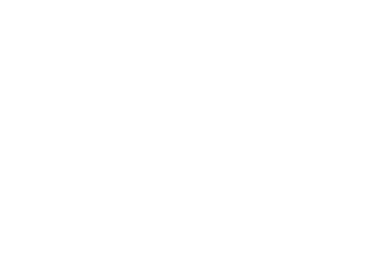大正時代にタイムスリップしたかのような『朧月』
大正ロマンあるいはゴシックロマンの世界観
『朧月(おぼろづき)』は、クリエイターでありボーカリストでもある「まふまふ」さんが、2018年に「YouTube」へアップした楽曲です。
歌詞は独創的な世界観です。
「不本意な相手と結ばれる」というシナリオは、大正ロマンあるいはゴシックロマンの世界観に通じるものがあります。
『朧月』の特徴点
荘厳な言霊(ことだま)の響きを味わう
『朧月』の特徴的な点を以下に挙げます。
まず、現代の日本人が使用しない古語が、ふんだんに使用されています。
つぎに、文(センテンス)・語句、特に固有名詞の使い分けが明確です。
そして、体言止め(語句の最後を体言で止めること)の多用です。
さらに、作品中で二人の恋愛をあえて書かないことによって、リスナーに想像させる余地がある物語構成になっています。
以上、これらの特徴的な点は、後ほど解説していきたいと思います。
※漢字の読み方がむずかしい語句には、ルビ(ふりがな)を振っておきました。
唐突に始まるAメロ!!

馴(な)れ初(そ)めを知らぬまま 薄紅点(さ)した宵時雨(よいしぐれ)
朔日(ついたち)に洗われて 真白になれたら
出典: 朧月/作詞:まふまふ 作曲:まふまふ
イントロが無く、いきなりAメロに入ります。
「フェンダー・テレキャスター」を思わせる、硬質なエレキギターの音が鳴りはじめます
「馴れ初め」とは、「恋人同士が知り合ったきっかけ」という意味です。
次の「知らぬ」という歌詞ですが、一般的な現代文法の言い回しだと「知らない」という語句になります。
つまり「ぬ」で終わるこの文は、古語です。
次の「点した」という言葉もあまり一般的ではないですが、「垂らした」と同じ意味です。
例えば「液体をスポイトで点した」というふうに使用します。
「宵時雨」は、2つの語句から構成される言葉です。「宵」と「時雨」です。
「宵」とは「日が暮れてから間もない時」という意味です。
「時雨」とは、「秋から冬にかけて急に降ったりやんだりする雨」という意味です。
また、「宵時雨」は、1つの文の終わりです。
このように、文を固有名詞などで完結させる技法のことを「体言止め」といいます。
Bメロ
幼き日々は貴方の傍(そば)
悠々(ゆうゆう) 夢の果て
出典: 朧月/作詞:まふまふ 作曲:まふまふ
Bメロは、特に際立った古語はありません。
「悠々」は、3種類の意味があります。
1.遠く遥かな
2.時間が久しく長い
3.ゆったりとしていて落ち着いている様子
この場合の意味は、上に挙げたどの意味でも通じると思います。
しかし、「夢の果て」という語句が後に続くことから、2の意味だと思います。
Bメロは、ボーカルにエフェクトがかかっています。
エフェクトの種類は、フランジャー(同じ2つの音をずらす)と軽いディストーション(音を歪ませる)だと思います。
このような処理が、楽曲の持つ幻想性を高めるのに一役買っています。
制限された字数で表現される悠久の情景
サビ
今宵は誰(た)がために踊るのでしょう
霞(かす)む 私は朧月
手繰(たぐ)り寄せる 朱殷(しゅあん)の糸口よ
貴方に続けと願う
出典: 朧月/作詞:まふまふ 作曲:まふまふ
サビの歌詞です。
日本古来からの文字芸術である「短歌」や「俳句」に似たニュアンスを感じさせる歌詞です。
少ない文字数から、リスナーのイメージ喚起力に直接訴える、良く選び抜いた言葉を使った歌詞でもあります。
「誰がため」という表現は、文語体です。
現代の口語体に訳すと「誰のために」という意味になります。
この言葉の表現は、ノーベル賞作家、ヘミングウェイの邦訳作品名『誰がために鐘は鳴る』という表現に代表されます。
「朱殷」とは、色の表現です。
時間が経って血の色のようになった朱い色のことです。
そのあとに「糸口」という言葉がくることから、否定的な意味での「赤い糸」、例えば結ばれない「赤い糸」が連想されます。
また、「私」が「朧月」だ、と表現しているので、この比喩表現は「擬人法」になります。
こういった修辞(レトリック)をいい塩梅に使用することによって、「主人公」と「私」が登場する「おとぎ話」あるいは「神話」のような、壮大なストーリーが展開されます。
歌唱の方に耳を傾けると、男性とは思えないような、澄み切った高音を出しています。
また、「誰がために」と「朱殷」のところで「コブシ」を入れています。
「コブシ」を入れることによって、メロディーに色彩感覚と情感を持たせることに成功しています。