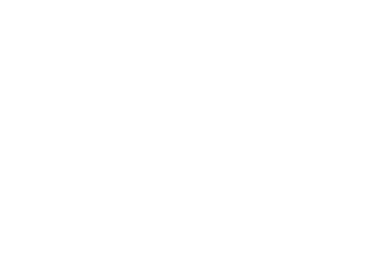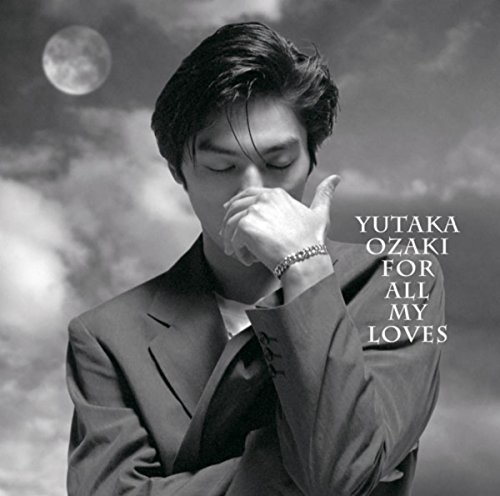「路上のルール」は現実社会の縮図である
今回は新たな境地がうかがえる楽曲、「路上のルール」をご紹介いたします。
独創的な比喩表現で、ファンならずとも魅了し虜にするのです。
ダイレクトに胸の奥底まで突き刺さる、「尾崎」といえばのフレーズは身を潜めています。
とはいえ、やはり世界観にハマってしまうのです。
自分の意思とは相反する、心の葛藤を絶妙に描写している楽曲ではないでしょうか。
自分の存在と居場所を探し続けていく
「路上のルール」は、1985年にリリースされたアルバム『壊れた扉から』に収録されています。
尾崎自身の誕生日前日、11月28日に発売したのです。
10代のあいだに制作された楽曲たち。
大人になる20歳を迎える前に、どうしてもアルバムにしたかったのでしょう。
曲中で、要所に「Yoh-!」と激しくシャウトするフレーズが印象的です。
「尾崎」ならではの、心の叫び。
夢へと彷徨う若者へのメッセージとも聴こえるのです。
求める真実とは?「路上のルール」を余すところなく読み解きます!
迷走のなかであがいている

洗いざらいを捨てちまって何もかもはじめから
やり直すつもりだったと街では夢が
もうどれくらい流れたろう今じゃ本当の自分
捜すたび調和の中でほらこんがらがってる
出典: 路上のルール/作詞:尾崎豊 作曲:尾崎豊
自分とは何か?原点とは一体...。
そう思い起こさせ、かつ意味深なイントロではないでしょうか。
「尾崎豊」らしい熱く激しいリズムながらも、どこか物悲しく淡々とした印象を憶えてしまうのです。
あらゆる人種が入り交じる、大都会。
現実社会と、どう向き合うかを問われているようです。
多種多様な人間模様の縮図を匂わせます。
それぞれの希望を抱き、都会へと旅立つ若者たち。
全てを投げ出し、ゼロからのスタートを切る一瞬を描写しているのでしょう。
行き交う人の渦に飲みこまれ、「こんなはずではなかった」と後悔の念も垣間見えます。
自分の力量を試すはずが、今では試され利用されているのかもしれません。
煌々と痛いほどに灯る街のネオンが、主人公の心に突き刺すのでしょう。
この足元には夢破れた人たちの積年の想いが重なりあい、影となり光をより際立たせているです。
そんな自分も、いよいよ未来を見失いはじめています。
あるべき姿を模索すればするほど、人の渦に抗えず巻き込まれているのです。
眩いばかりのキラキラと光り輝く街のネオン。
主人公にはくすんだ光が目に映っているのでしょう。
同調や協調を自分の意思とは関係なく、不条理に求められる人間社会。
そう訴えかけているのかもしれません。
自分の存在とは?改めて見つめ直すことに気づかされるのです。
もがき続ける主人公
互い見すかした笑いの中で言訳のつくものだけを
すり替える夜瞬きの中に何もかも消えちまう
出典: 路上のルール/作詞:尾崎豊 作曲:尾崎豊
中身のない人間関係を揶揄しているのでしょうか。
日常の平凡な会話の一端ではないようです。
ともすれば、自分の周囲に対してへの反感も含まれているのかもしれません。
現実を直視できず、大人の社会に対してへの反発ともいえるのです。
自分が追い求めるモノが周りには受け容れられない、苦悶とも感じとれます。
相手の気持ちや心を探りあい、ただその場を取り繕っているだけだといっているのでしょう。
心のこもっていない関係性や付き合いなど、一瞬で泡となり消え去ってしまうのです。
たった2行の歌詞ですが、あらゆる心情が凝縮され「路上のルール」を象徴していると思えてなりません。
現実を目の当たりにする主人公
鏡の世界にうつる姿
街の明りの下では誰もが目を閉じ闇さまよってる
あくせく流す汗と音楽だけは止むことがなかった
今夜もともる街の明りに俺は自分のため息に
微笑みおまえの笑顔を捜してる
出典: 路上のルール/作詞:尾崎豊 作曲:尾崎豊
見てみぬふりをする社会のルールに向け、警鐘を訴えかけているのでしょうか。
「臭いものにはフタをする」。だんまりを決め込む大人のルール。
擦り切れ、やりきれない主人公の心。
生きにくい現実社会と、いかに向き合うか葛藤しているのです。
混沌としたまま日常を過ごすなか、「音楽」だけは自分を裏切らなかったのでしょう。
ギターをかき鳴らすと、無意識のうちに涙が頬をつたうシーンも思い浮かびます。
憤りを憶えながらも、鏡にうつる自分の姿をジッと見つめるのです。
そこには、「笑えよ」と語りかけてくるもう1人の姿。
ゼロからのスタートを切った頃の自分自身が語りかけてきたのです。